先日の自分のTwitterの呟きをまとめたい。
未来を読み解くキー
メタップス佐藤さんの言うところの、未来を読み解く「お金」、「テクノロジー」、「感情」という3つの要素。この中で「お金」はクリアされつつある。「テクノロジー」もすでにある。「感情」という個人が持つ、とても読みづらいものをどう操作、あるいは読み解くかがキーか。
そのためには”流れ”を作ること。流れは人の感情を突き動かす。だが、流れを作るにはソーシャルで、ある一定の流れを作ることもできないことはないと思うが、資本は今でも必要条件。資本のある企業が動けば、自然とその流れが出来上がっていく。今のAI、VRはまさに典型的な例だろう。
流れを作ることで感情を動かすのは、崇高な理念とビジョンも然り。誰もがそういう世界になるべきだと思っていて、それを大々的に発信する人物が現れると、人々の感情は大きく揺さぶられる。一つの例は今のアメリカ大統領選挙でのトランプの活躍。政治は感情を理解するのにふさわしいとはそういうこと。
ヒトラーはその感情操作(大衆操作)に非常に長けていた。ヘリコプターを飛ばすなどして非日常感を演出、興奮しやすい夜の時間帯に演説を行うことや、同じことをひたすら繰り返し発言するという、計算された演説手法。人々の感情をまるで手のひらの上で転がし遊ぶように。
日本の政治家で言えば、田中角栄。だが田中角栄の場合、ヒトラーと異なる点は1対マスではなく1対1という関係性において、その感情を動かした点だろう。簡単に言えば、ヒトラーはトップダウン型式による感情操作、田中角栄の場合はボトムアップ式の感情操作。
感情的に反応するのかそうじゃないのかというのは、どこに矢印が向いているのかの違いだろう。自分に矢印が向いていれば裏切られたと感じる。自分の中にあるベッキーのクリーンなイメージが浮気という信頼を失うようなことをされ、クリーンなベッキーが浮気ベッキーになってしまった。
だがここで注意したいのが、それはあくまで「あなたの”中”のイメージ」だという点。外に矢印が向いていれば、「あなたの”中”のイメージ」のベッキーは変わらないのでは。よって、理性で考えることができる。この矢印の使い分けが重要。
この矢印の使い分けが、ヒトラーみたいなトップダウン式で感情操作しようとする人らへの対処策であろう。だが難しいのは、この矢印の使い分け以前に感情で判断してしまう点だ。だから、感情が起こる前の正しい矢印の方向を定める必要がある。そこで有効な一つの手段は知識をつけること。
知識を作ることで、判断基準を持つことができる。判断基準とは、自分の中に地図を作ることでもあると思う。その地図の中に知らない国があれば、その国を判断しようがない。その国のある人物を知っているなど関連した情報を持っていれば、一つの判断材料になりうる。

自分が持つ地図と感情
自分の中の地図が沖縄の大きさしかなければ、東京ましてやアメリカなど遥か未知の世界。未知の世界はよくわからない。よくわからないから怖い。怖いという感情はよくわからず、判断がつかないため(自分の中の地図にはその国の名前がない)否定的な意見につながりやすい。これが感情の正体でもある。
感情で否定的な意見を言う人の多くは、地図がないことに起因するのではと思っている。だからそれ自体をさらに否定しても意味はなく、その地図を拡げてあげれるような質問であったり、アドバイスを行うことが有効。
テクノロジーの進化はこの地図を初期段階から拡げてあげられることが素晴らしい点だ。Google検索によってすぐに情報を得ることができ、Instagramでは友人の状態、Twitterでは現地のリアルな情報、Newspicsでは様々な地図を持った人々の様々な意見を見ることができる。
自分を知るとは、自分と宇宙の関係性の中でその地図を描くことだ。
そうか、死が怖いというのも死を知らないからか。
チャレンジすることや、知らない地に行くこと、知らない人に会うことが怖いのも、それらを知らないから、わからないからか。
なんで怖いんだ?なぜ、知らないことが怖いにつながる?
知っているとは、勉強したことがあったり、経験したことがある。その経験のなかで、問題が起こったときにその解決も経験したことがある。つまり、解決策を知っていることで、安心感を持つことができる。
知らないのは、なにか問題が起こった時への対処がわからないことによる不安感につながる。恐怖の正体は不安感。その不安を払拭するために経験者や友人に相談したりする。
相談することで一つの解決策を知れたり、後押しされたり、元気づけてくれたり。その過程で不安感は減っていく。減るといっても完全になくなる訳ではない。
そして不安レベルがある一定ラインまでくれば、チャレンジにつながる。そのラインとはどこか?見える化できるものか?
感情のパラメーターみたいなものか。だが、これは感情という“感じ“なだけであって、実態のない幻想でもある。人はこの実態のない幻想に操作されている。そう、子供とはこの幻想を知らない素晴らしい存在なのだ!
世の中になにか残す者には天才かバカしかいないというのも、幻想への対処方法を熟知している者か、幻想?へ?ってそもそも知らないような者ということか。
成功者の中には子供っぽい人が多いといのは、無邪気な好奇心で知らないことにたいする恐怖、不安感という幻想を持っていないため。答えは幻想への対処にある、ということ
じゃあ、どうすればそういう人材を育成できるか。子供の教育においてはその好奇心をつぶさないこと、社員教育においては、、なんだろう
いや、そういう人材が多すぎてもだめだ。そう、恐怖を感じるから人はそのリスクヘッジを考えることができ、生存の目的を達成することができる。不安感という幻想は人を生き延びさせるものでもある。要はバランスの取りどころが重要
幻想に取り憑かれてる人には、「それは自然なことなんだ。ありのままで。」と伝えよう。まぁ、これも投げやりだが、、笑
地図の描き方こそ”自分らしさ”
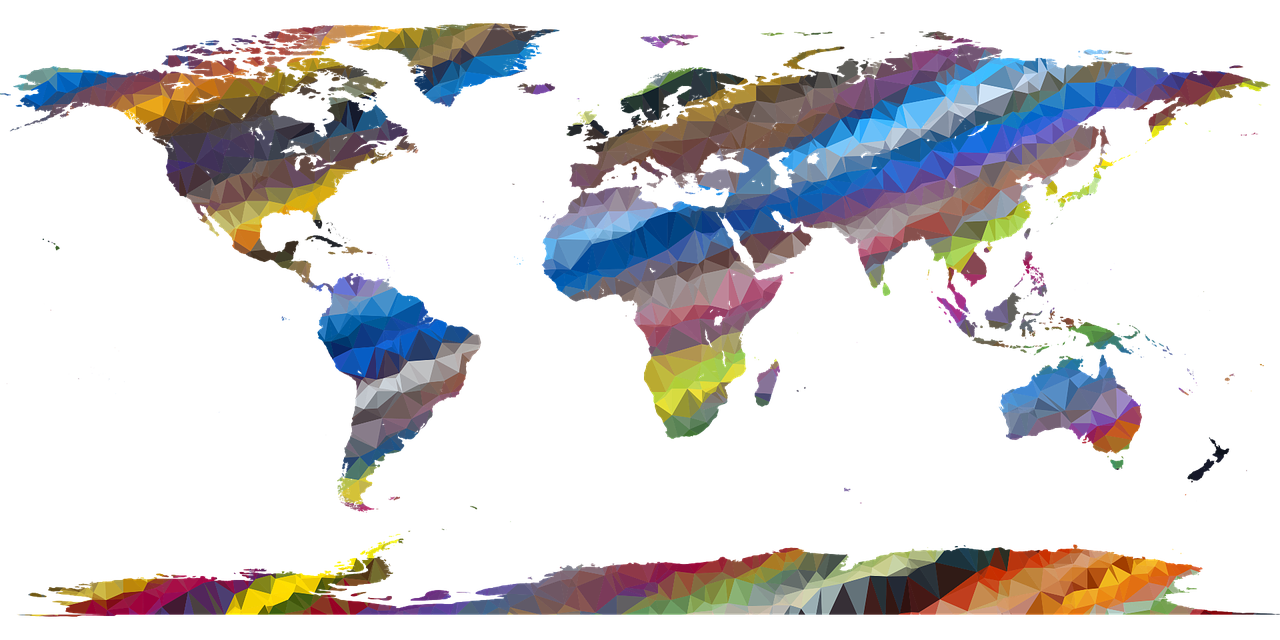 だから、無理に幻想を取っ払う必要なんてない。それは健全な心の働きなんだ。Let It Go!行き着くとこは、ありのままでいること。ありのままでというのが健全な生き方であり、結果的に人類を存続される。
だから、無理に幻想を取っ払う必要なんてない。それは健全な心の働きなんだ。Let It Go!行き着くとこは、ありのままでいること。ありのままでというのが健全な生き方であり、結果的に人類を存続される。
そう、このありのままでや自分らしさみたいなのがわからないから、更に迷走するんだ。自分らしさっていうのはわかる、だけど自分らしさってなに?みたいな。
その答えは経験にある。経験することによって 自分と世界との関係性を構築していく。 その結果自分の中の地図を描くことができる。 その地図の“描き方“こそ自分らしさである
その人らしさとは、その人がどういう描き方で地図を描いているかであり、その地図をもとにどう自分以外の世界を見ているか、だ。
その世界の見方というアウトプット部分が人と違えば違うほど、変人や異端者と呼ばれたり、天才とも言われたり、要は独自性があることにつながる
偉大な芸術家や画家などの持つクリエイティビティーとはまさにその独自性の最もたるもので、人と違う見方で人の訳のわからないものを生み出したから希少性が高い故に、価値が高い。
「希少性=価値が高い」
常に人と違う道を選ぶというのは、価値の高いことを生み出すにはまさに合理的な方法でもある。
なるほど、ならば天才は幼少期に孤独が多かったという点も、情報が少ないが故に地図の描き方が他の子とは異なる結果になり、独自性を得たという結果を生むことになったのか。世界を他の子とは違う風に見ていた、と。
Tweetをまとめただけなので、とりとめのないブログになってしまった。
▼関連記事
シンギュラリティサロンに行ってきた!第二弾「心を創った天才」
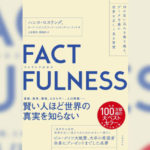
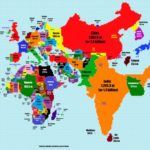



Be First to Comment